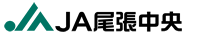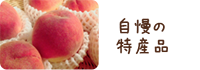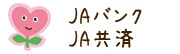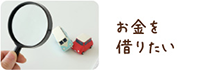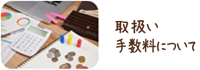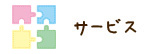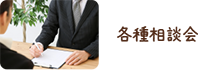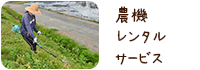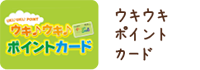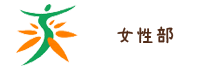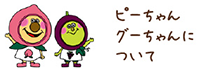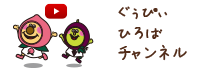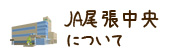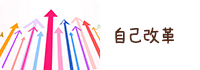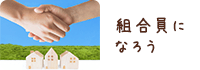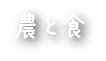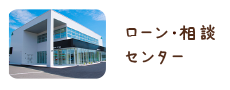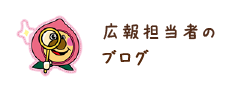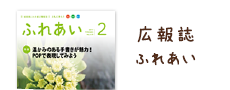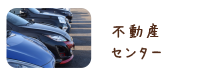カンキツ類の栽培
[2022.04.01]
●営農技術指導員 須崎 静夫●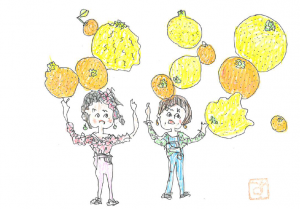
カンキツ類も温州ミカンのように栽培できます。変わり種のコレクションも乙なもので、三宝柑(サンポウカン)・仏手柑(ブッシュカン)・文旦(ブンタン)・椪柑(ポンカン)・檸檬(レモン)などは絵になりそうです。大小さまざまなトゲがあるので注意してください。1本の樹に色んな品種を高接ぎしても楽しめます(図1)。一部例外もありますので、ご容赦を。
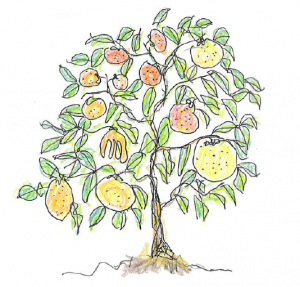
▲図1 高接ぎ
1本の樹にいろいろな品種を高接ぎすることもできます
※種苗法を遵守してください。登録品種の苗木を購入して自家増殖(接ぎ木)するには、育成者の許諾が必要な場合があります
●整枝せん定
寒さの緩んだ3月下旬頃に行います。枯れ枝・徒長枝・内向枝・下垂枝・秋枝・たくさん実のなった枝などを外します。枯れ枝を見つけ次第外すと病害の予防にもなります。
前年にならせ過ぎて花つきが心配される場合には、4月中旬につぼみを確認しながらせん定しても良いでしょう。日当たりが悪いと、下の方の枝からの発芽は期待できません。
樹が大きくなります。苗木の頃から、あまり大きくしないように心掛けると良いかもしれません。
●芽かき
強くせん定した場合などに不要な不定芽が出たら、早めに取り除きます。
●摘蕾(花)
1枝に5花以上の花つきが多い場合には、葉っぱの横から出ている花蕾(直花)を摘んだり、枝を揺すったりして適当に落とします。新梢の先についている花(有葉花)を残しましょう。授粉は不要です。
●摘果
生理落果後の7月以降、大きすぎず、小さすぎずの良い果実を残します。
とりあえず荒摘果で、葉のない所や裾なりの果実を落とします。
仕上げ摘果では、品種本来の重さが300gなら葉果比は100くらい、のように、「葉果比は果実の重さの1/3=葉っぱ1枚で果実3g、小さい葉っぱなら、なりを少なく」を目安にすると良いでしょう(図2)。
葉果比を変えると果実の大きさも変わってきます。グレープフルーツはその名のとおり、グレープ(ブドウ)のようになります。
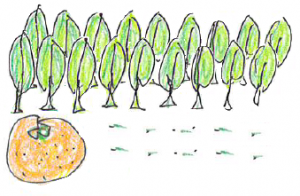
▲図2 葉果比
果実1個を品種に適した大きさ・重さにするための葉っぱ枚数の目安
中晩生カンキツの場合は、葉っぱ1枚で果実3gくらい。例えば果重300gなら、葉果比は100
●枝吊り
果実の重みで垂れた枝を竹竿や支柱、ヒモで吊って支えます。
●収穫・貯蔵
年内に成熟した果実から収穫して、予措(軽く乾燥)します。年明けに成熟する種類は、着色・減酸程度・寒さと相談します。寒さが厳しいと、果皮障害(霜焼け)・苦み・ス上がり(果汁の減少)・落果などが起こるので、これらが起こる前の12月末頃に収穫して新聞紙に包み、適当な段ボールや木箱に詰めて、5~10℃のところで貯蔵し、酸が減るのを待ちます(図3)。
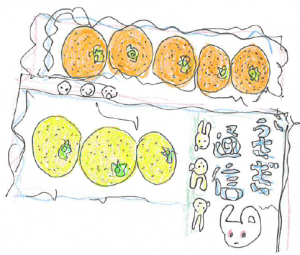
▲図3 貯蔵
寒さを避けるため、早めに収穫して酸が高い場合には、新聞紙等に包み段ボール・木箱に入れて、5~10℃くらいのところで貯蔵して、酸が下がり、食べ頃になるのを待ちます
寒さ対策がきちんとされて(図4)、品種本来の成熟期までならせると、美味しい果実がなりますが、鳥に食べられるかもです。
食べ頃は、「イヨカン・ポンカン・はるみ:2月」「不知火(しらぬひ)・せとか・ハッサク:3月」「甘夏・ブンタン:4月」「夏ミカン・日向夏(ひゅうがなつ):5月」です。
「レモン(はちみつレモン)」「スダチ」「カボス」「ユズ(柚子胡椒・ゆずジャム・ゆず茶・ゆずみそ・ユズ風呂)」「ダイダイ(しめ飾り)」「紀州ミカン・ブンタン(鏡餅)」「キンカン(のどあめ)」などは、時期が来れば収穫できます。冬至やお正月などの物日に合わせると良いでしょう。
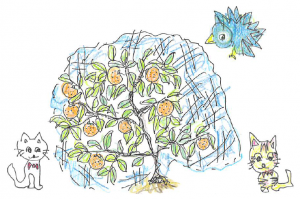
▲図4 網掛け
寒さよけには、寒冷紗・タイベックなどを、鳥よけには、防鳥網を被覆する
●病害虫防除
防除・施肥こよみ(※)を参考にしてください。農薬を使用する際には、農薬使用基準を遵守し、農薬使用履歴を記帳してください。
ハダニ類、アザミウマ類、カイガラムシ類、カミキリムシ類や葉・果実に赤褐色の病斑のできる、かいよう病が発生します。よく観察して、防除してください。
※防除・施肥こよみについては、お近くの営農生活センターへお問い合わせください。HPからも入手できます。
●施肥例
発芽前(3月:元肥)、果実肥大期(7月:追肥)、収穫前後(10月:お礼肥)に施用します。
●ひとこと
カンキツ類について、いろんな方がいろんな分類をしています。
以前の露地栽培では、ミカンの後に(中晩生)カンキツでしたが、12月の「早香:はやか」や「南香:なんこう」のように、ミカンより早く食べられるカンキツが出てきました。ややこしいですね。
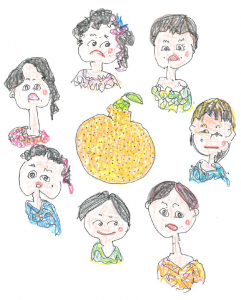
▲図 一番首を長くして待っているのは、どのお嬢さんでしょうか?