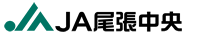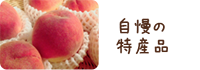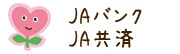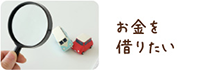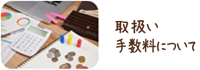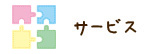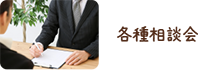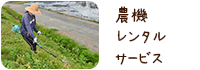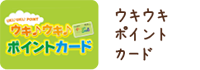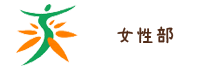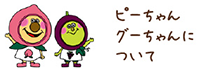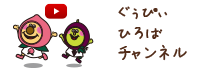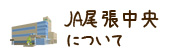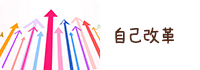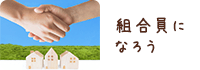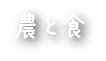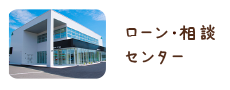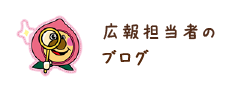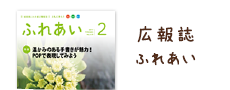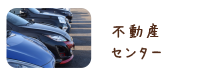キクの管理 ~ハガレセンチュウ防除~
[2019.02.01]
●営農技術指導員 大澤梅雄
質問
去年、露地秋ギクに褐色の大きなV字形病斑が下葉に現われ、蕾が見える頃には上の葉まで枯れました。商品性が落ちてかなりの損害です。今後の対策を教えて下さい。
回答
この症状はハガレセンチュウ(葉枯線虫)の被害かと思われます。ハガレセンチュウの症状は、特徴があるので比較的見分けやすいです。キクの下葉が枯れた時には、病気のみならずセンチュウも疑ってみて下さい。
1 特徴
ハガレセンチュウはキク、アスター、ヒャクニチソウ、ダリアなど主にキク科植物を加害します。地下部の根に寄生するネグサレセンチュウとは違い、地上部に寄生して被害を与えます。同様のものにイチゴメセンチュウ、イチゴセンチュウ、イネシンガレセンチュウなどがあり、これらを含めてハセンチュウと呼ばれています。
2 生態
成虫の体長は1mm程度で小さく、体形はミミズの様。うど芽や地上に落ちた被害葉の中で越冬し、春、茎が伸び出す頃、土中に泳ぎ出て、雨の跳ね上がりや雨水を伝って茎を登り葉に到達し、気孔から侵入して植物組織内に入ります。口針を細胞に突き刺して加害します。雨が多いと発生も多くなります。
3 症状
葉の葉脈に区切られた部分が褐色または黒色になります。一見褐斑病に似ていますが、ハガレセンチュウは直線的な模様、褐斑病は不正形になります。
被害は下葉から始まり、次第に上位葉に及び、株全体の葉が枯れてしまうこともあります。落葉せずいつまでも茎についているのが特徴です。
4 耕種的防除
(1) 連作をしない。
(2) 被害葉並びに圃場に落ちている枯葉を取り除き焼却します。
(3) マルチフィルムを張り、泥の跳ね上がりを防ぎます。
(4) 被害株はもちろんのこと、その周辺の株も次作の親株にしない。
5 農薬による防除
被害を受けた畑の株を掘り上げ親株として使う場合、特に注意が必要です。
親株養成中、1㎡あたり3,000倍にうすめたガードホープ液剤2リットルを潅注すると良いでしょう。処理回数は2回以内です。処理後根系への薬剤移動を促すために、出来るだけ早い時期に1㎡あたり5~20リットルの水をさらに潅注してください。
散布薬については登録農薬がありません。