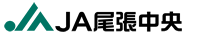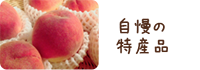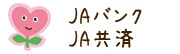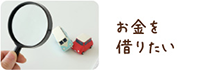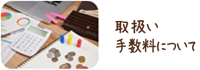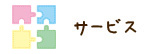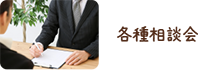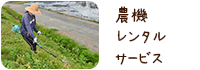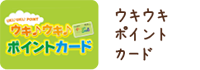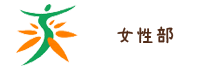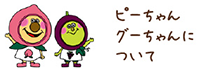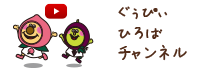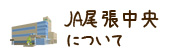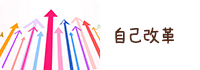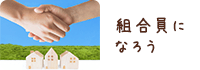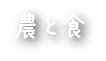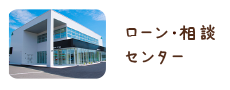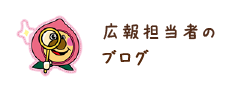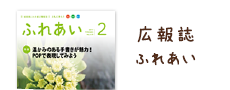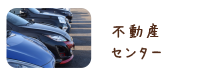マツの管理 ~病害虫防除~
[2018.06.01]
●営農技術指導員 大澤梅雄
質問
庭に植えてから25年経過した黒松があります。若いうちは病気知らずで元気に育ちましたが、数年前から調子が悪くなってきました。毎年秋から葉が黄色っぽくなり、春に赤みを増してきますが、落葉はほとんどありません。病気でしょうか。
回答
一気に木が枯れてしまったということではないので、マツクイムシの被害ではないと思います。毎年同じような症状を繰り返しているということなので、カビによる葉枯れだと思います。葉枯性の病気には、赤斑葉枯病(写真)、褐斑葉枯病、すす葉枯病、葉枯病、葉ふるい病(図)など色々あります。病名を同定する際の目安をまとめておきましたので参考にして下さい(表)。しかし、どの症状も非常によく似ていて、目で見て病名を同定することはなかなか難しいです。
質問の症状は恐らく一般的な「赤斑葉枯れ病」ではないかと思われます。
1 対策
マツの葉枯性病害発生条件は多湿です。したがって、多湿にならないような栽培環境を整える必要があります。また、伝染源を絶つよう庭の衛生管理に努めて下さい。
(1) 栽培環境の改善
a 空気中の多湿
数年間剪定をせず、放置したマツは葉が密生します。こうなると樹冠内が多湿となり、病気を誘発します。適度なせん定で針葉を減らし、風通しを良くします。
b 土壌中の多湿
今までの相談事例では、概ね葉枯性病害が発生した庭のマツは、植え付け年数が数十年以上経過したマツでした。
植え付け当初は、土壌中に空気が適度に含まれ排水性も良く良好な生育を示します。しかし、年数が経つに従い雨や踏圧などの影響により土が締まり、土壌中の空気が追い出され排水性の悪化で根が腐り、その影響で樹勢が弱まり病気になりやすくなります。対策としては、①雨水の排水を促すためにマツの周囲に明渠を掘る。②空気を土中に送り込むために検土杖のようなもので穴をあける。③樹冠下にコケが生えてきたら土壌を乾燥させるためにコケを除去する等です。
(2) 衛生管理
罹病葉や落葉などを集めて焼却しておきます。
2 農薬による防除
本病に対する登録農薬はありませんが、葉ふるい病との同時防除を目的に、キノンドー水和剤40の散布によって、本病の拡大を防ぐことができます。
胞子が飛散する5~10月中に500倍液を月1回の4回散布するか、6~7月に集中的に4回散布します。完全防除には2~3年を要します。
参考図書・文献
1 天野孝之,作山健,周藤靖雄(2008):「原色花卉病害虫百科7花木・庭木・緑化樹②」,農文協
2 岡田充弘(2008):ミニ技術情報「マツの葉枯性病害と防除」,長野県林業総合センター
3 陶山・福井(2007):「庭園木クロマツの新病害-褐斑葉枯病」,島根県中山間地域研究センター
4 徳重陽山・清原友也:「マツ葉枯病の防除試験」,林業試験場研究報告第135号
 |
| ▲写真 赤斑葉枯病 |
 |
| ▲図1 葉ふるい病のイメージ図 |
 |
| ▲表 マツの葉枯性病害一覧 |