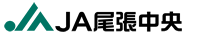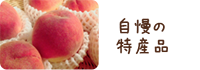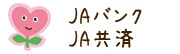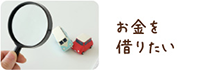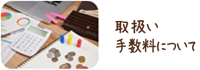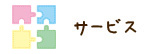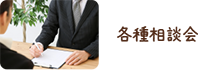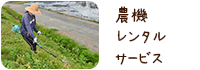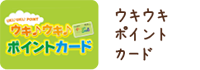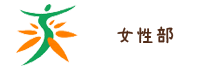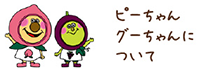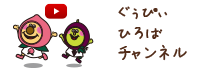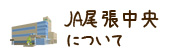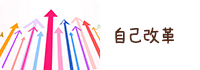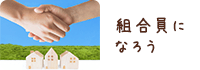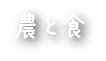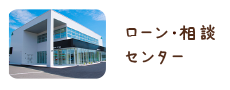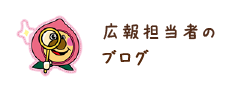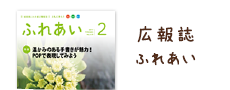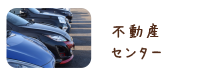7月の果樹だより
[2017.07.01]
●杉山文一営農技術指導員
<スモモ栽培のポイント>
尾張中央農協管内では、夏を楽しむ果実として家庭果樹でスモモ栽培をしている事例が見られます。栽培のポイントをまとめましたので、参考としてください。
1 スモモ栽培の条件
スモモは、開花が早く環境に大きく左右されます。表1に、栽培の条件をまとめました。苗木を植える時の参考にしてください。
スモモは、ウメについて開花が早く、遅霜に遭遇すると結実不良になります。開花時期に、-2~-3℃程度の低温に遭遇すると霜害になります。
スモモは、根群が浅く停滞水に合うと樹勢が弱ります。耐水性に弱いので、粘土質でなく通気性のよい排水良好な土壌だと生育が良くなります。
2 スモモの生育状況と年間作業
ソルダムを基準に図1にまとめましたので、参考にしてください。「貴陽」と言う品種は傘かけをしますが、無袋で栽培します。収穫時に灰星病やシンクイムシ類が発生しますので防除は注意が必要です。
3 主要品種の特性
栽培品種の選定は、8月のホームパージを参照してください。「ソルダム」が一般的ですが、1品種でも結実し易い「ビューテイ」や「サンタローザ」が家庭果樹向きと思われます。新品種の「貴陽」は、大玉で美味しい品種ですが、交配可能な品種が「ハリウット」しかないので交配品種に注意して下さい。
4 栽培管理のポイント
(1)開花・結実の管理
スモモは、ビューテイやサンタローザのように1品種でも結実し易い品種もありますが、大部分の品種は自家不親和性で他品種の花粉が必要です。1品種では結実が不安定です。表2を参考に受粉樹の品種選定してください。また、結実を良くするためには授粉作業が必要です。
花粉を採取して人工受粉をすると、結実の向上となります。
(2)着果管理
予備摘果と仕上げ摘果をしますが、最終着果量は、図2のようにしてください。
摘果は、形が良く、大きく下向きの果実を残し、小玉果・変形果・キズ果・病害虫被害果・結果枝の基部の幼果を摘果します。
結実が確認できたら、予備摘果をおこないます。予備摘果~仕上げ摘果と2~3回おこなうと大きな美しい果実が成ります。仕上げ摘果は、満開から50日~60日頃を目安におこないます。
着果量の目安は、大石早生などの中玉品種は、中長果枝に8~10cm間隔に1果、短果枝で3~4芽に1果残します。大玉品種のソルダム・貴陽・太陽などは、中長果枝で10~12cmくらの間隔で1果、短果枝で1果、花束状短果枝で1果残します。
(3)新梢管理
樹幹内部に光が入るように、また樹形を整えるため、5月に捻枝・摘芯を、6月に新梢の切除を、8月下旬に秋期せん定おこないます。
スモモは、樹間の下部から強い新梢が発生しやすいので、樹間の基部の新梢を重点に20cm程度残して切除します。
(4)施肥管理
開花や生育が早いため、枝の充実を図る目的で、9月上旬の礼肥を重点として化成肥料を、基肥を11月に有機主体肥料を施用します。枝の充実を図るためには、貯蔵養分の蓄積が重要です。貯蔵養分の蓄積を図るには、礼肥が重要となります。礼肥は、速効性の化成肥料を少し多めに施用して下さい。
(5)整枝せん定
樹形は、3本主枝で各主枝に亜主枝を2本づつ配置した開心自然形が主体です。また、今年発生した強い発育枝を図3の様に切り返すと中・短枝を形成します。
ソルダムにおいては、すべての枝を強めに切り返す。20cm以下の枝は2分の1程度の切り返しをする。先端の新梢は40cm以上伸びる切り返しがポイントです。
(6)病害虫防除
土壌病害の白紋羽病害、果実を腐らす灰星病、ヒメシンクイ類やカイガラムシ類が発生しますので防除に注意して下さい。防除は、3月から5月と各品種の収穫前の防除がポイントです。樹勢が秋に急に弱った場合は、根を腐らす白紋羽病の可能性がありますので、一度根を掘って見てください。根に白いカビが生えていたら、白紋羽病の可能性がありますので土壌消毒が必要です。
 |
| ▲表1・表2 |
-690x631.jpg) |
| ▲図1 |
 |
| ▲図2・図3 |